設立趣意CONCEPT
ビジョン
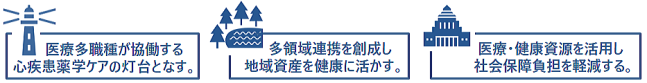
スローガン
共に創ろう。心疾患薬学ケアの未来を
目的
当機構は、心不全を始め心疾患の発症及び増悪の薬学的介入による抑止を目標とし、心電図やバイタルの判読による薬学ケア・フォローアップの充実、薬局の機能拡充、多職種連携の推進等に関わる諸活動の実践をもって、健康の増進、福祉の向上、臨床薬学の振興に寄与することを目的とする。
設立趣意
〝心不全を始めとする心疾患の発症及び増悪〟は、医療、社会へ深刻な影響を及ぼしています。
循環器系疾患による死亡者数は23万人超と総数の23.9%に達し、悪性新生物〈腫瘍〉に次ぐ第2位を占めています。
中でも「心不全」による死亡者数は脳血管疾患に匹敵し、心疾患での死亡原因の1位ともなっています※1。
また、心不全の再入院率が、退院後6カ月以内で27%、1年後は35%との調査報告※2がなされておりますが、2040年頃には医療・福祉分野で100万人程度の人材不足が推定※3されるなか、医療資源の偏在とも相まって、心不全患者数の急増や再入院の反復に対応しきれなくなる可能性も否定できません。
このことは「心不全パンデミック」の到来を予見させるものであり、もはや社会的課題と云っても過言ではないでしょう。
一方、社会保障費増にも影響する〝心不全の再入院〟の患者側要因で心疾患治療上の課題でもある、治療薬服用や塩分・水分制限の不徹底に対しては、薬剤師が、心電図を簡便に計測できる機器やバイタルの管理が可能なPHR※4を始めとするICTを積極活用することで、適正服薬や生活習慣改善の指導を効率的に実施でき、医師をはじめ医療多職種との円滑な情報共有と併せて、薬剤師の介入が効果を上げ得る事象も多いと考えられます。
故に、薬剤師を軸に6万余店の医療資源である薬局を活かすことで、心不全等心疾患の発症及び増悪の薬学的介入による抑止の実現が可能であると思料し、薬学ケア・フォローアップの充実や多職種・多領域連携の促進に関わる諸活動推進のための包摂的な活動基盤となすべく、この度当機構を発足させるに至った次第です。
ここに、当機構が達成すべき4つの使命や活動を提起します。
1つ目は、心不全等心疾患の発症および増悪の抑止と健康増進の基を成す、心電図・バイタル判読や健康状況把握による適切な薬物療法の充実に向けた「心疾患薬学ケアの構築、並びにフォローアップの実践」です。
2つ目は、活動を担える優良な人材の育成とともに、適正かつ円滑な実施に向けた技能品質の維持・向上を図るための「教育や顕彰、並びに資格や基準の認定」です。
3つ目は、地域・地産を活かす新たな医療・ケアシステムの共創に向け、業界・学域を超えた実ある多職種・多領域連携促進のための「ステークホルダーのネットワーク形成、並びに活動を支えるICTの開発や整備」です。
4つ目は、社会保障費の削減や医療資源の効率活用を目途に、政策・公的施策や民間事業との広範な協調、健康増進活動の協働や医療支援等に資する「薬局機能の拡充、並びに地域医療支援の統合的展開」です。
心不全等心疾患の発症及び増悪抑止への対応は、高齢化の急速な進展と重なりつつ希求の度を一層深めていくものと推察され、故に当機構に課せられた使命は極めて重いものと考えます。
日頃より諸課題と向き合う皆様と、業界や領域を超え闊達に意見を交し合い、連携・協働の実現へ先ずはその一歩を踏み出すことこそ、今日の医療、そして社会課題の解決への嚆矢になるものと確信いたします。
目的に向け、共創の志を一にする皆様の当機構へのご参画、そしてご支援を心よりお願い申し上げます。
令和6年12月吉日
一般社団法人日本心不全薬学共創機構
漆畑 俊哉:代表理事/薬剤師・博士(薬学)
※1 令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況ほか(厚生労働省)
※2 心不全診療Q&A:第一章 慢性心不全の疫学(中外医学社)
※3 令和4年版 厚生労働白書(厚生労働省)
※4 PHR:Personal Health Record
バナースペース
一般社団法人日本心不全薬学共創機構
〒250-0011
神奈川県小田原市栄町一丁目14番28号(NTT小田原ビル1階)